これからの教育を考える上でも、キーワードとされているのが「多様性理解」。
「みんな違ってみんないい」が大切というのは誰もがうなづくことだと思います。
しかし、実際には、いじめはなくならず、人間関係の問題はあとを立たない。
小・中学生と関わっていると、必ずといっていいほど「スクールカースト」の話が出てきます。
わたしの尊敬する研究者が、「多様なモノにふれ、受け入れる」ということ自体が、自らの発達の上で大切なポイントであるとおっしゃっていました。
本当の意味で、「みんな違ってみんないい」ってどういう社会なのでしょうか。
こどもたちと対話する上での良本を紹介したいと思います。
13歳の僕の視点から多様性について対話しよう「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」
ベストセラーエッセイなので、多くの人がご存知かと思います。
特にわたしが、大切にしているのは第5章。
エンパシーについて語られる章です。
ぼくが、エンパシーとは「誰かの靴を履いてみること」と答えたのが秀逸で、多くの人がハッとさせられた章です。
本当に自分と違う考えや立場を「受け入れる」ということは、難しい。
自分の内側にある言葉で語ることができるか。
行動を変えることができるか。
自分の人生を歩むということは、自らの人生を自らの意思で進むことと思いますが、そこに他者や社会への貢献ができて初めて充実を感じられるとわたしは思います。
社会課題がより複雑になっている未来、若い人たちがこの力がとても大切なのではないかなと思います。
舞台はイギリス。日本とイギリスの教育の違いをまざまざと感じさせられることで驚きを感じられます。
同年代である主人公にも感情移入しながら読めるので、家庭での対話のネタとしても、学校や多年代での対話のネタにもなるでしょう。
この本にも演劇教育のシーンが出てきて、ちょっと演劇教育が話題にもなったんですよね。
友達がLGBTだったら?性の多様性について考えたい「ぼくがスカートをはく日」
わたしが主宰する団体三重四日市リトル・ミュージカルに所属する高校生が読んで教えてくれた小説作品。
主人公は12歳の男の子グレイソン。彼の抱えている自分の性別を巡る秘密。
それが、学校の演劇で女神役を演じることで、より顕在化し、そして自信を得ていく。
内在している自分に自信を得ていく一方で、周りの反応は様々。
一筋縄ではいかないリアリティがそこには詰まっている。
エンディングを読んで、どう思うだろうか?それぞれの状況で意見が全く違うだろう。
主人公がたくましくなっていく姿とは裏腹に、事態は複雑になっていく様子にハラハラ!
前述の高校生は、主人公がスカートに履き替え「教室のドアを開けた」という、最後の一文が印象的であったという。
その時の主人公の感情、そこに広がる光景が、一気に自分の中にも流れ出す、読書の素晴らしさを体感できます。
その体験から性の多様性、それに対する周囲の理解の多様性について考えるきっかけになるのでは。
キャラクターの丁寧な描写から、それぞれへの共感と立場を探った上で、対話するスタイルも良いと思います。
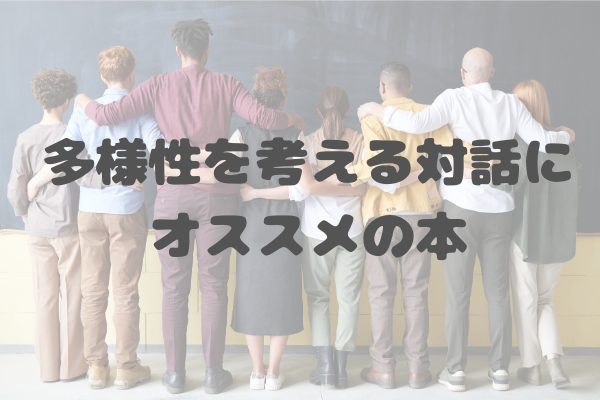

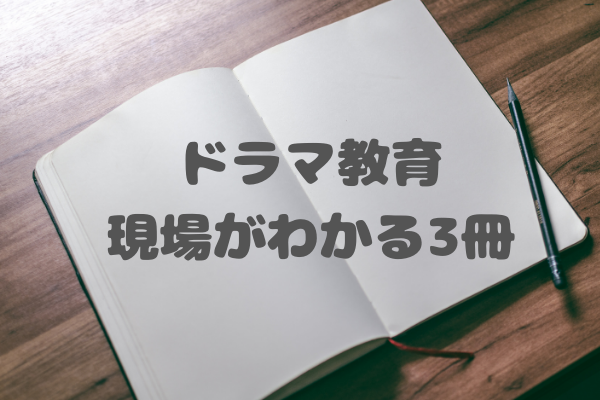

コメント